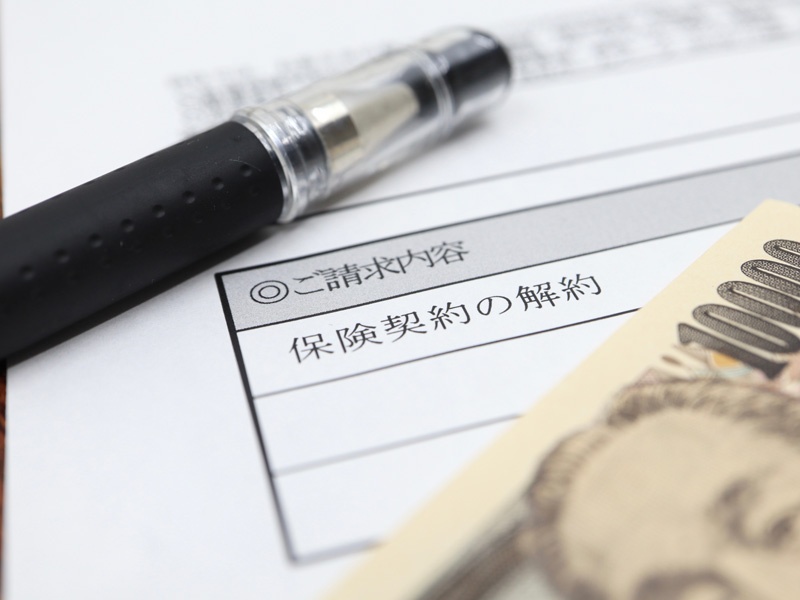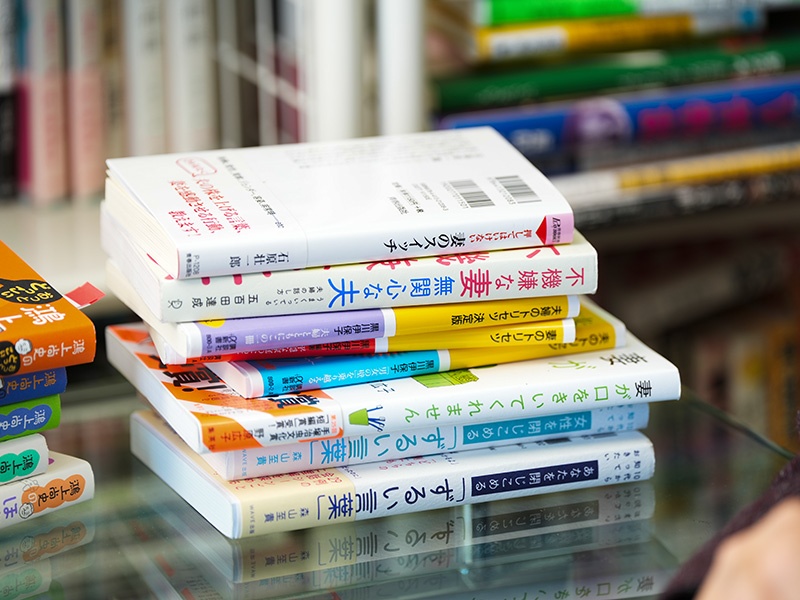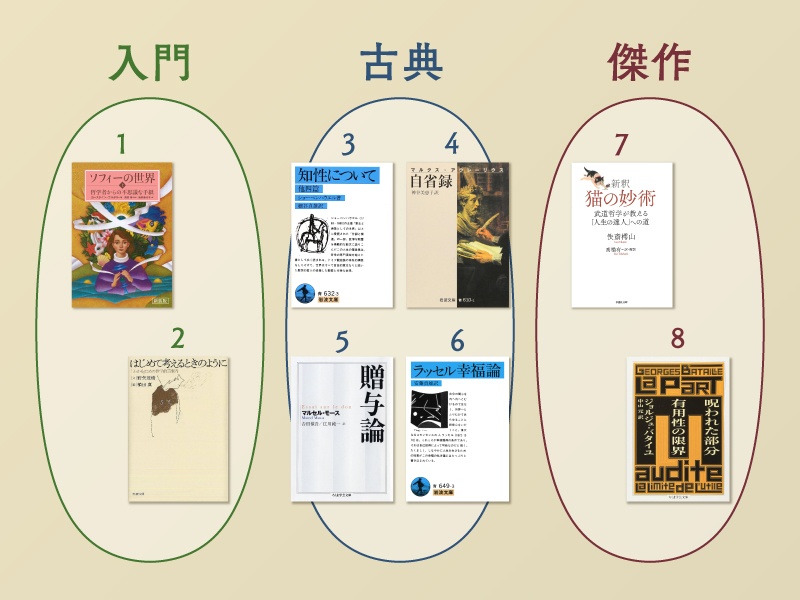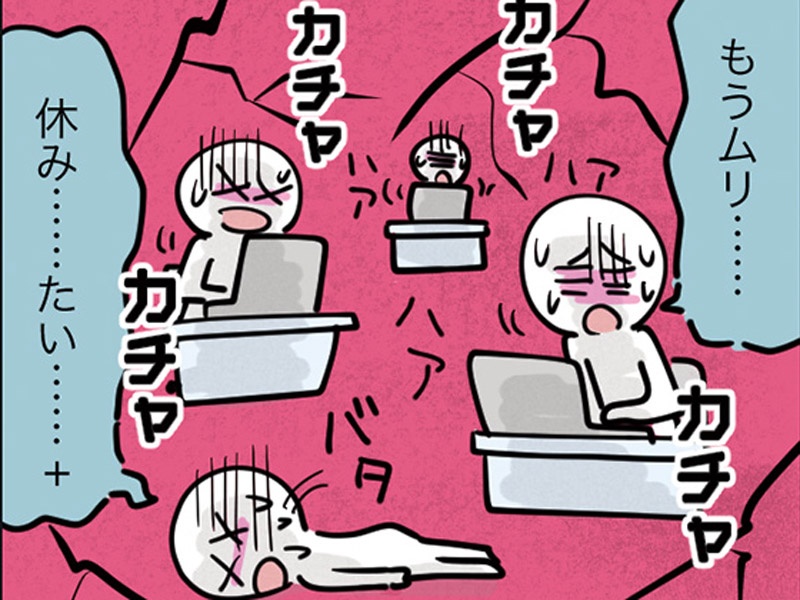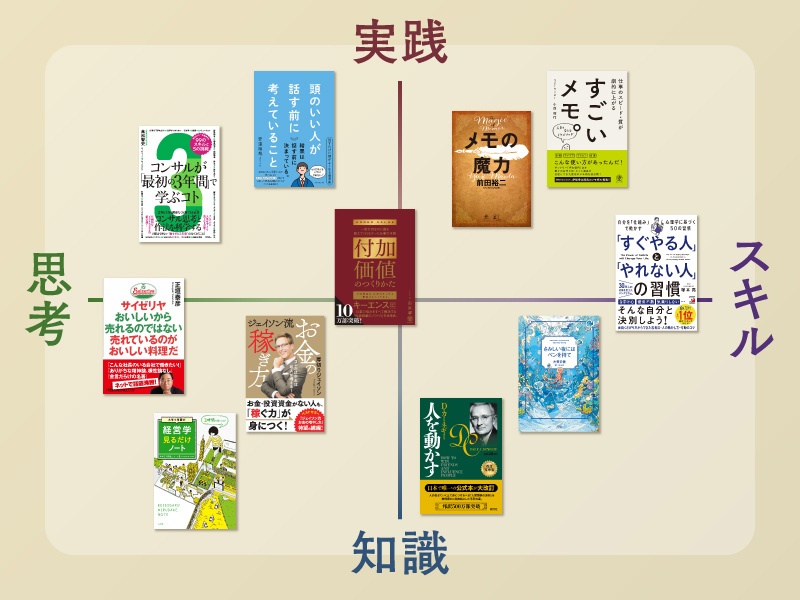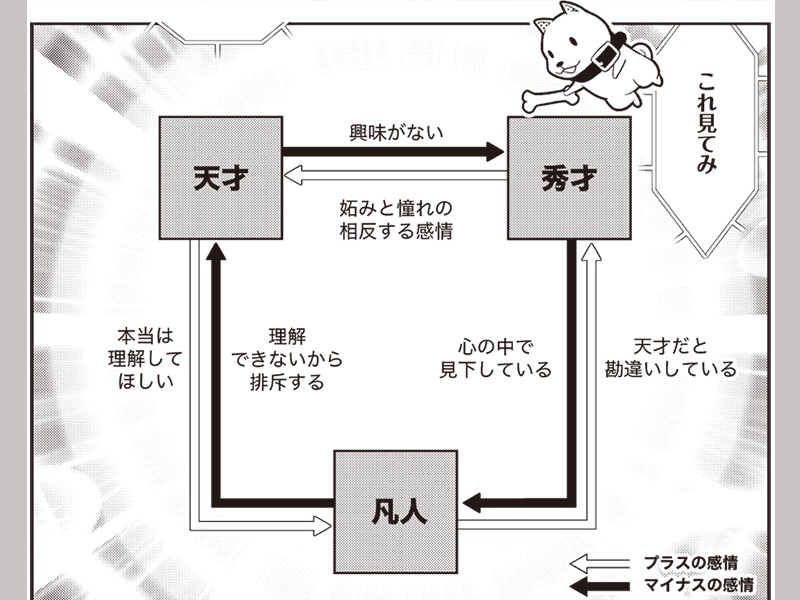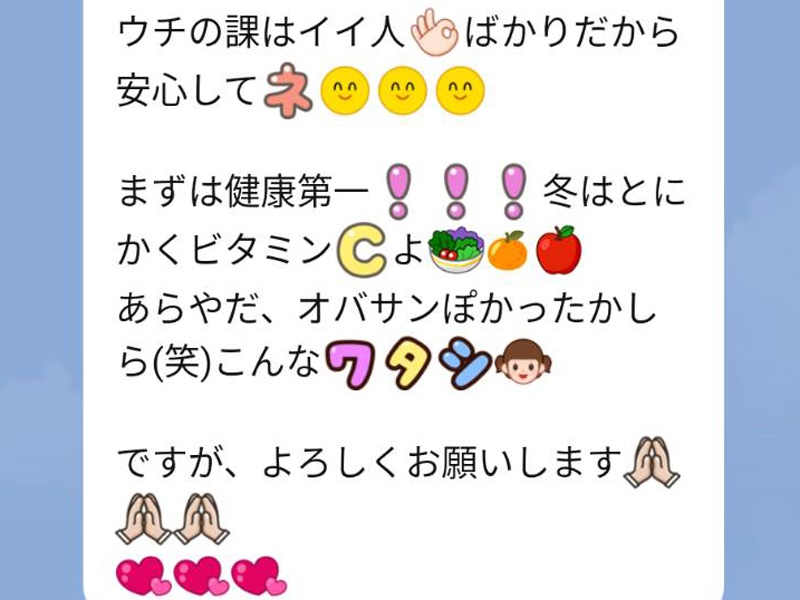-

読む、日経の本ラジオ
「永遠の命」を手にする4つのシナリオ 『「不死」の講義』
-

まいにち「はじめに」
はじめに:『ゼロからわかる マネーの常識 NISA、イデコから保険、税金、住宅ローンまで』
-

BOOK Selection
GWに「30代が読んでおきたい、おすすめビジネス名著」記事まとめ
-

昭和人間のトリセツ~厄介な自分や周囲との付き合い方
昭和人間はなぜ大昔のことを「ついこのあいだ」のように語るのか
-

この保険、解約してもいいですか?
プロほど入らない「○○保険」 貯蓄取り崩しを嫌う心理の不合理
-

まいにち「はじめに」
はじめに:『Azure Stack HCIテクノロジ入門 Azureとの連携によるハイブリッドクラウド』
-

東京大改造2030 気になるあの再開発エリア、どうなる?
「麻布台ヒルズ」必見の建築デザイン6選 世界的設計事務所が共演
-

ユニクロ物語
「泳げない者は沈めばいい」 ユニクロ柳井正と古参幹部の別れ
人気記事ランキング
-
 1
1「泳げない者は沈めばいい」 ユニクロ柳井正と古参幹部の別れ
-
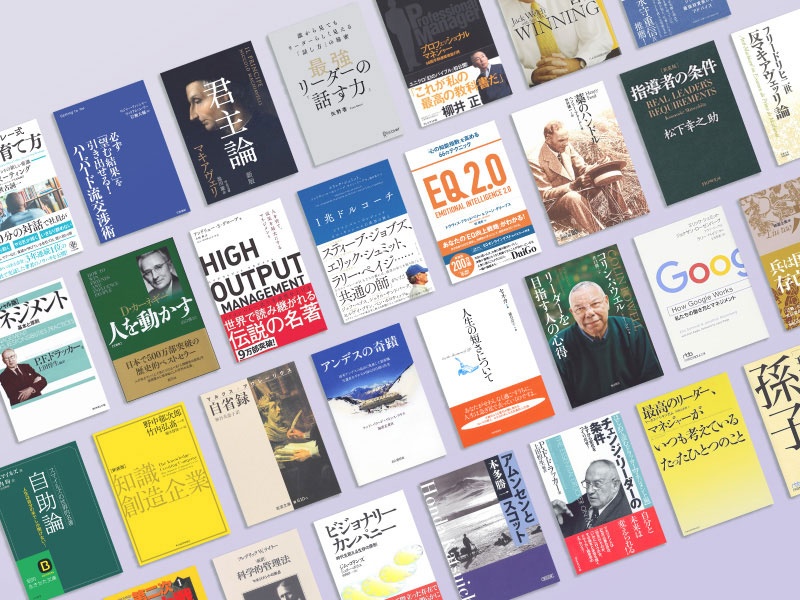 2
2管理職が読んでおくべき、おすすめのビジネス書 記事まとめ
-
 3
3GWに「30代が読んでおきたい、おすすめビジネス名著」記事まとめ
-
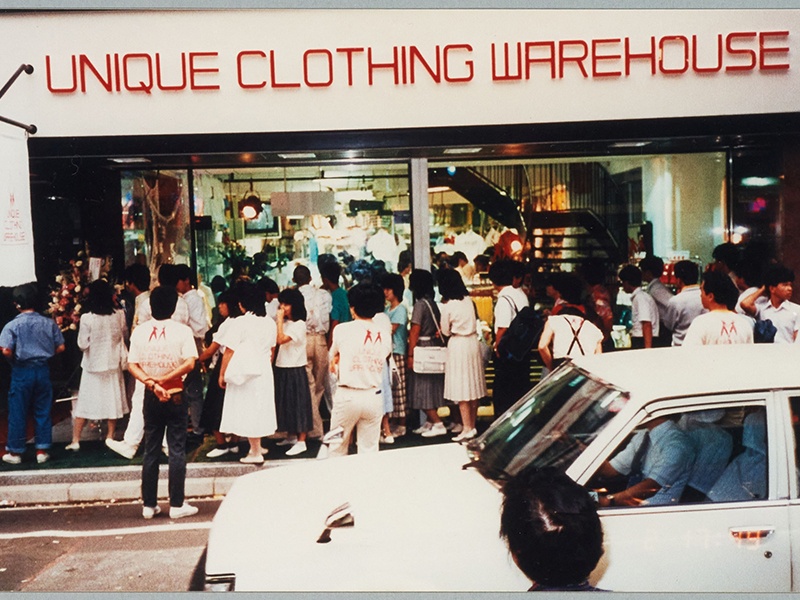 4
4「金脈をつかんだ!」叫ぶ柳井正 ユニクロ1号店、開店秘話
-
 5
5話題の本 書店別・週間ランキング(2024年4月第3週)
-
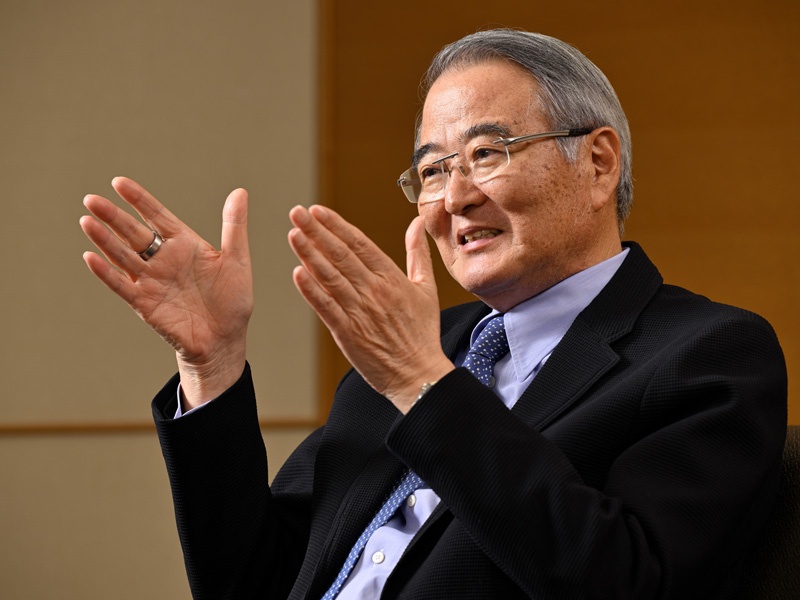 6
6「お前、もう帰れ!」東大卒の開発者が料亭で叱られた
-
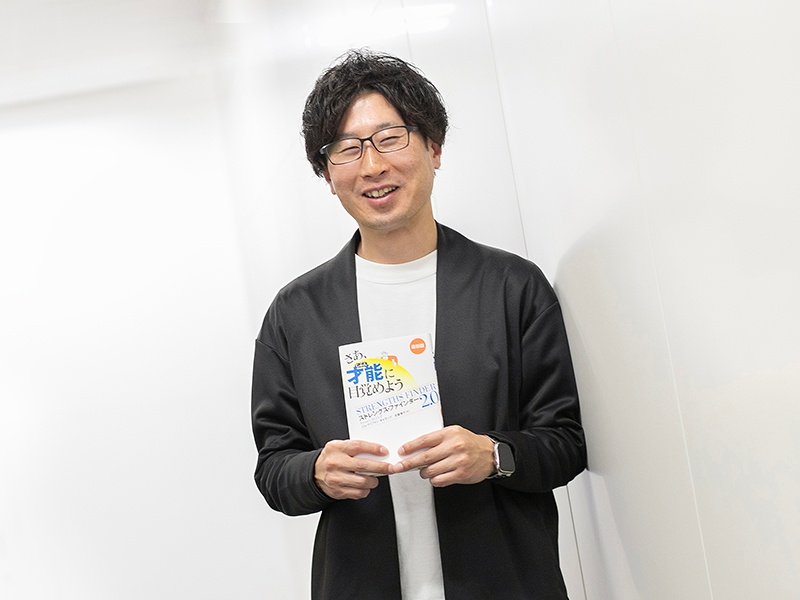 7
7立命館守山で『さあ、才能に目覚めよう』活用、教員に起きた変化
-
 8
8ユニクロ 苦戦する海外店舗、撤退寸前からの反転攻勢
-
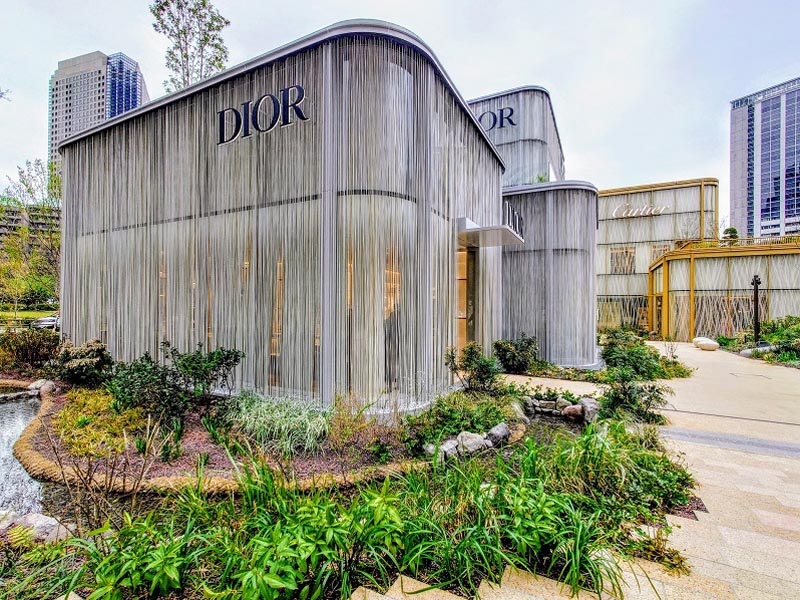 9
9「麻布台ヒルズ」必見の建築デザイン6選 世界的設計事務所が共演
-
 10
10落合陽一、現代の茶道をデジタルネイチャーで読み解く
-
 11
11新社会人が読んでおくべきおすすめのビジネス書 記事まとめ
-
 12
12昭和人間はなぜ大昔のことを「ついこのあいだ」のように語るのか
-
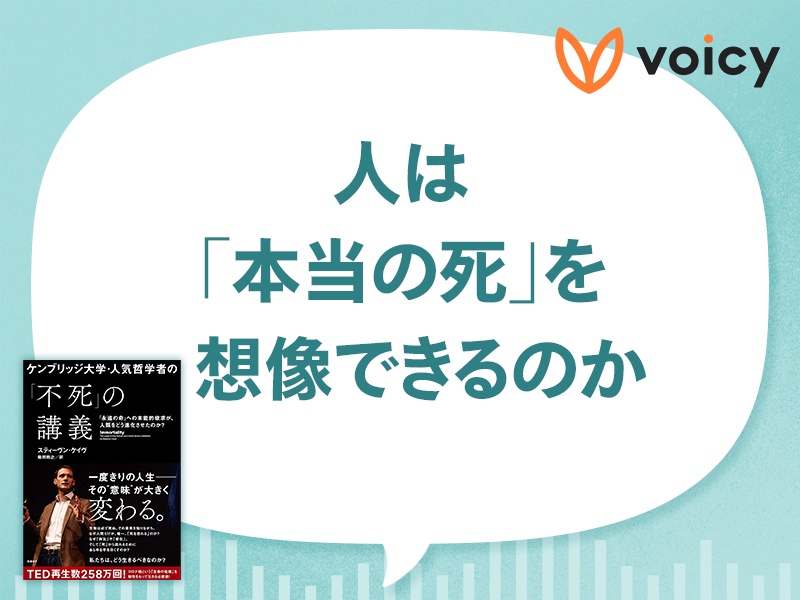 13
13すべての人に訪れる「死」と向き合う 『「不死」の講義』
-
 14
14マッキンゼー調査で判明 日本企業のM&Aに求められる戦略
-
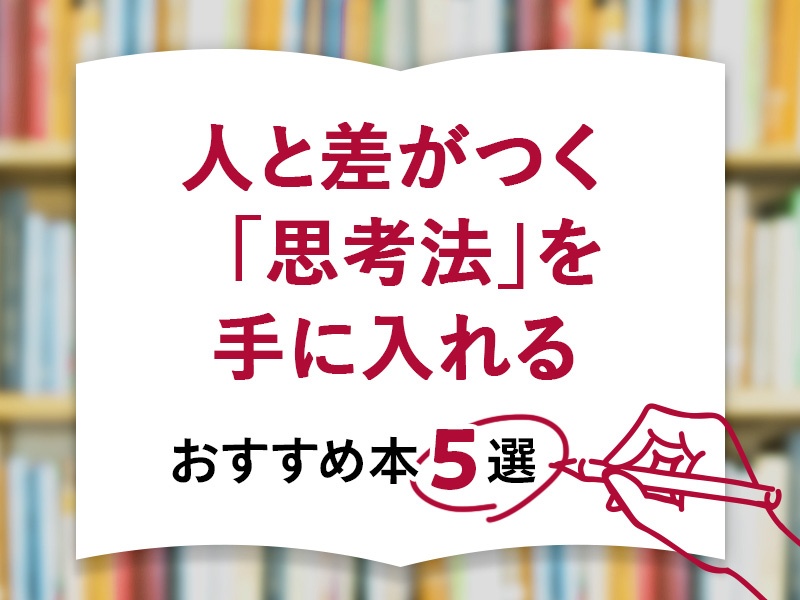 15
15人と差がつく「思考法」を手に入れる、おすすめ本5選
「本日」は2週間以内に公開した記事が対象
旧サイトをご利用のお客様へ
旧サイトは4月21日より、新サイト「日経BOOKプラス」に統合されました。旧サイトに掲載されておりました書籍ならびに関連情報は「日経BOOKプラス」にてご覧いただけます。
書籍をお探しの場合は、画面上の虫眼鏡アイコンから検索機能をご利用いただき、書名/著者名/ISBN/その他キーワードでお調べください。関連資料やサンプルファイル、正誤表をお探しの方は、各書籍のページ下部からダウンロードしていただけます。
今後とも「日経の本」ならびに「日経BOOKプラス」をよろしくお願いいたします。
企業経営にはSDGsやESGの視点が必須
SDGs・ESG関連書籍はこちら
https://info.nikkei.com/books/sdgs_esg/