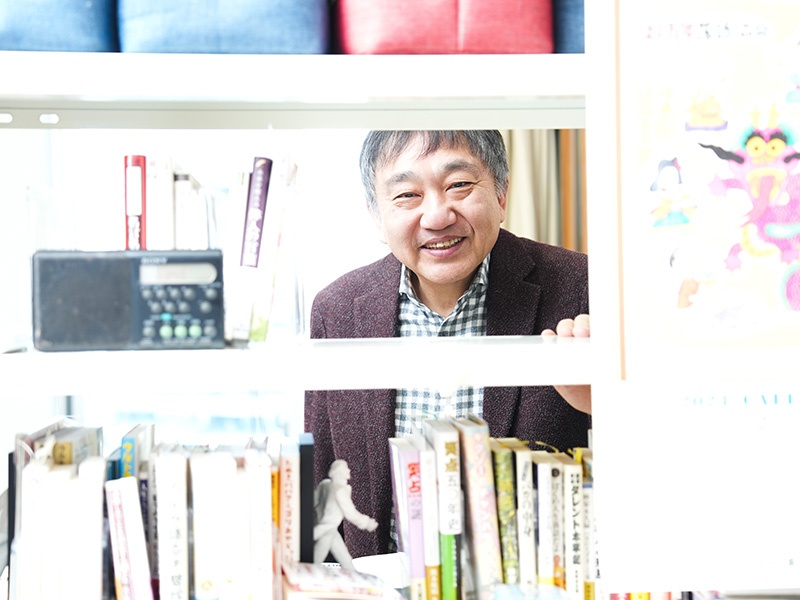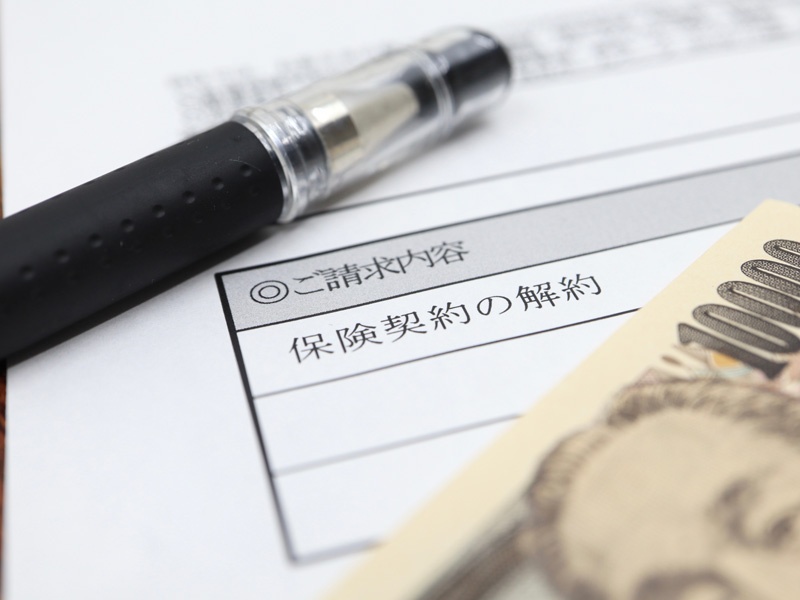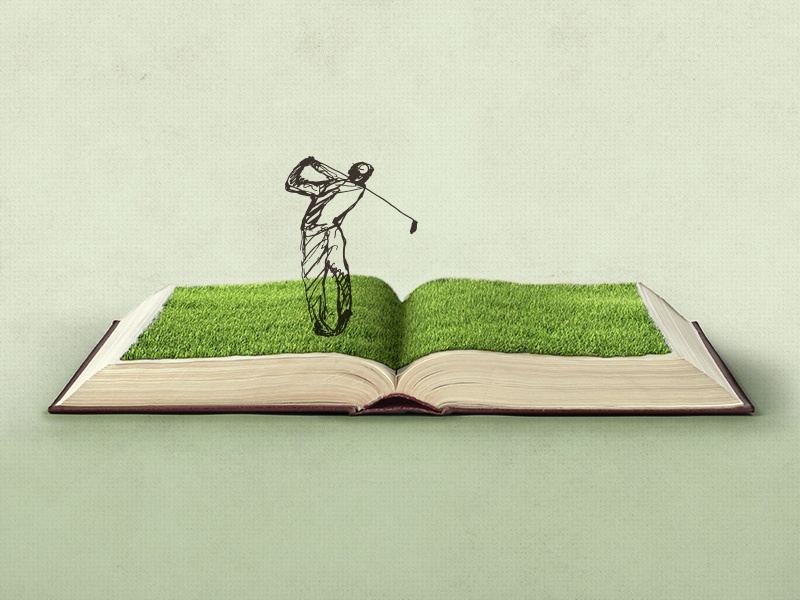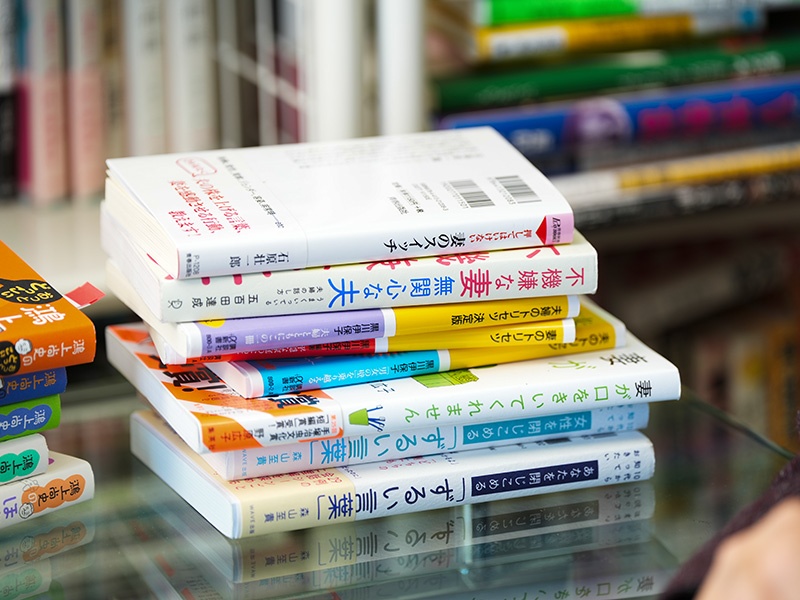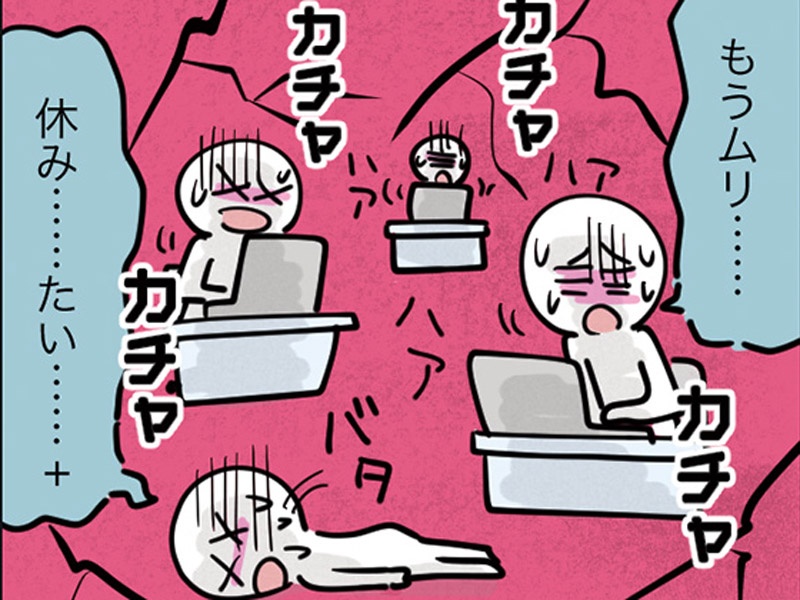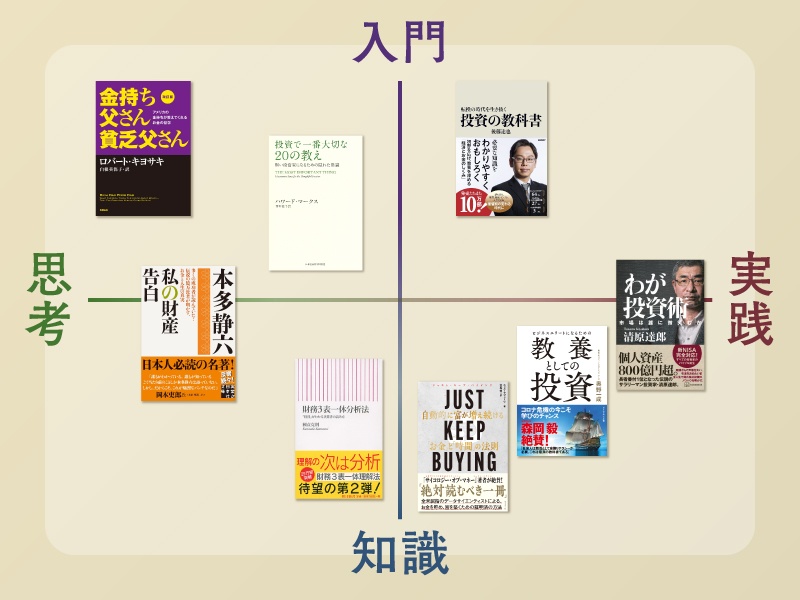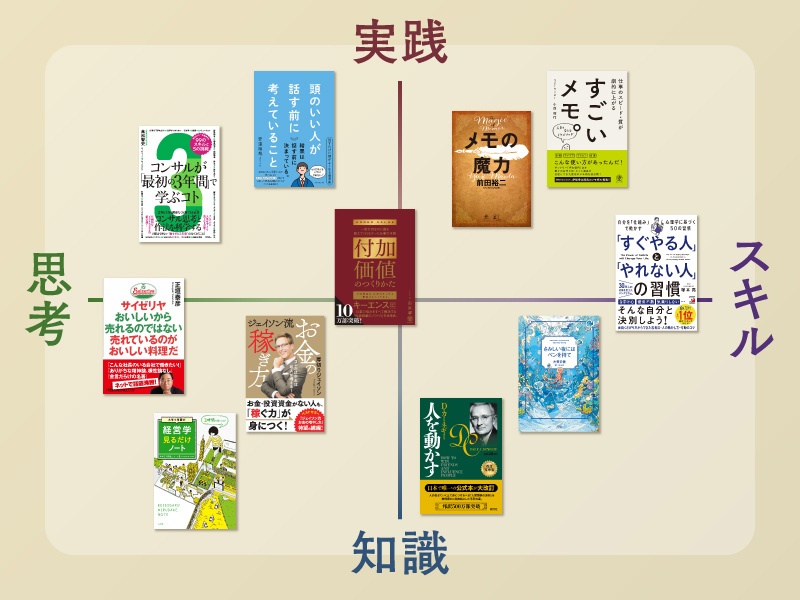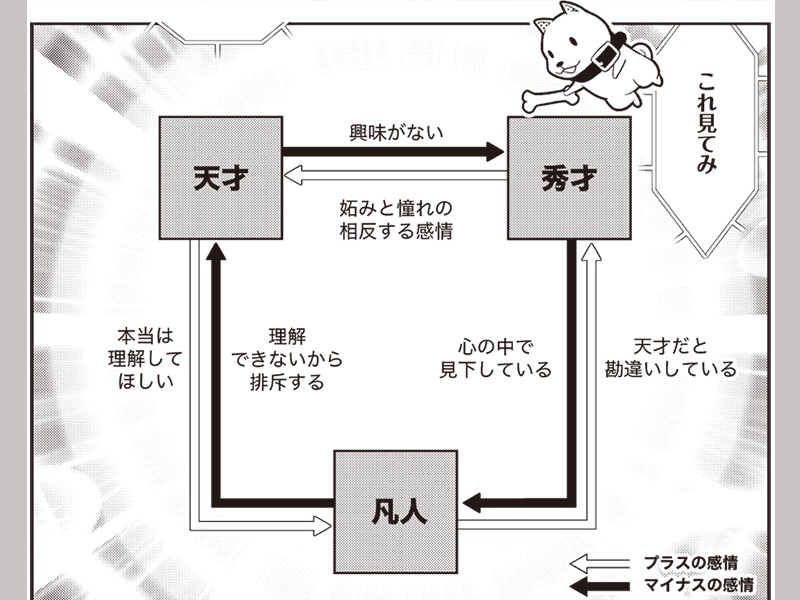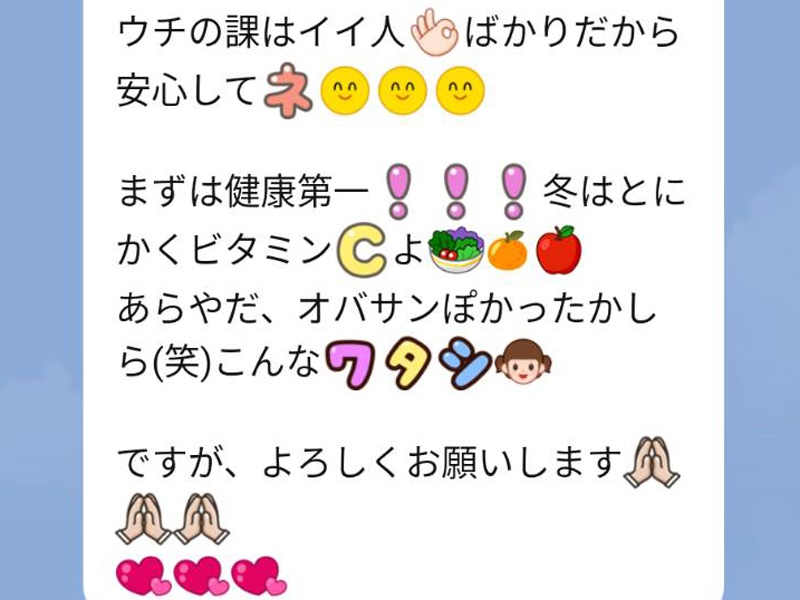-

マッキンゼー 価値を創るM&A
マッキンゼーが分析 日本企業のM&Aの傾向とこれから
-

石原壮一郎 昭和の尻尾と夫婦関係を考える本
もはやひとごとではない物語 石原壮一郎が選ぶ夫婦関係を見直す2冊
-

まいにち「はじめに」
はじめに:『美術館に行く前3時間で学べる 一気読み西洋美術史』
-

まいにち「はじめに」
はじめに:『ジオストラテジクス マンガで読む地政学 世界の紛争・対立・協調がわかる』
-

この保険、解約してもいいですか?
競馬・宝くじと比べれば明快 生命保険は行動経済学的に不合理
-

名門校の推薦図書
フェリス阿部教諭「今なお、この本を読むことには大きな意味がある」
-

まいにち「はじめに」
はじめに:『ソフトバンク もう一つの顔 成長をけん引する課題解決のプロ集団』
-

この街に、この本屋さん
東京・吉祥寺 街々書林 旅心を刺激する魅惑の本屋さん
人気記事ランキング
-
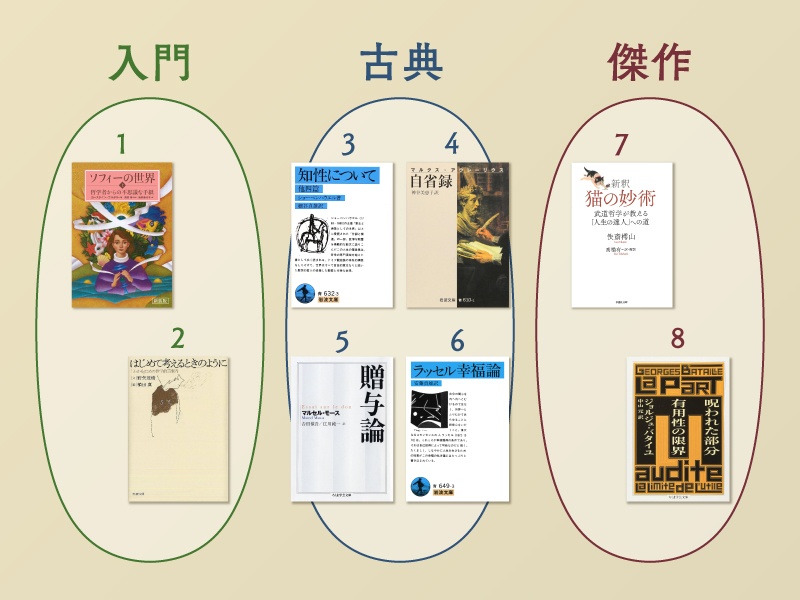 1
1一度は読むべき「哲学」の名著 カリスマが選ぶ入門・古典・傑作8冊
-
 2
2同志社生協 大学らしい品ぞろえと「町の本屋さん」の役割を意識
-
 3
3落合陽一、現代の茶道をデジタルネイチャーで読み解く
-
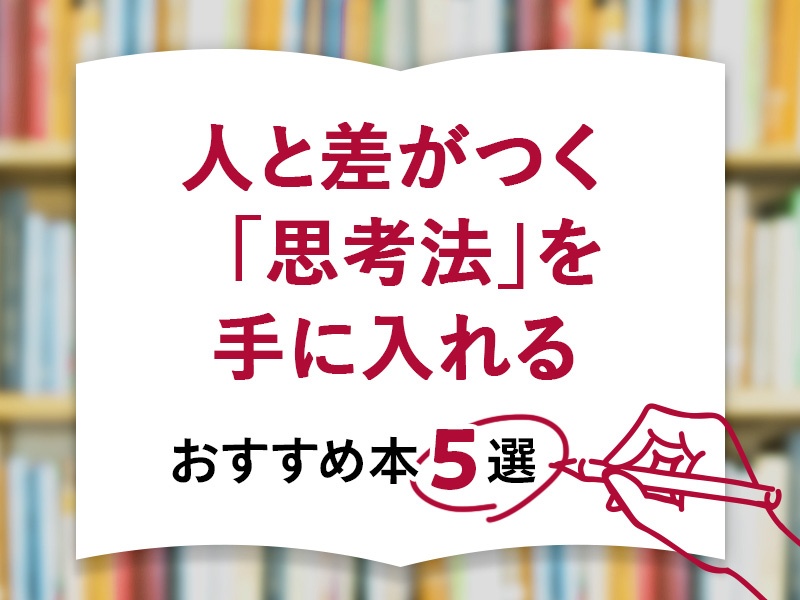 4
4人と差がつく「思考法」を手に入れる、おすすめ本5選
-
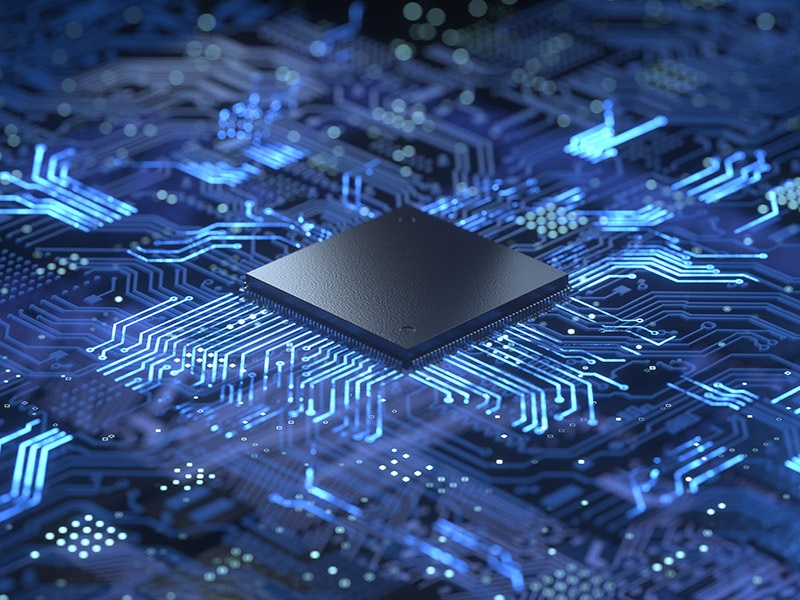 5
5ラピダスの2つの不安 日本の半導体企業が追求すべきこと
-
 6
6フェリス阿部教諭「今なお、この本を読むことには大きな意味がある」
-
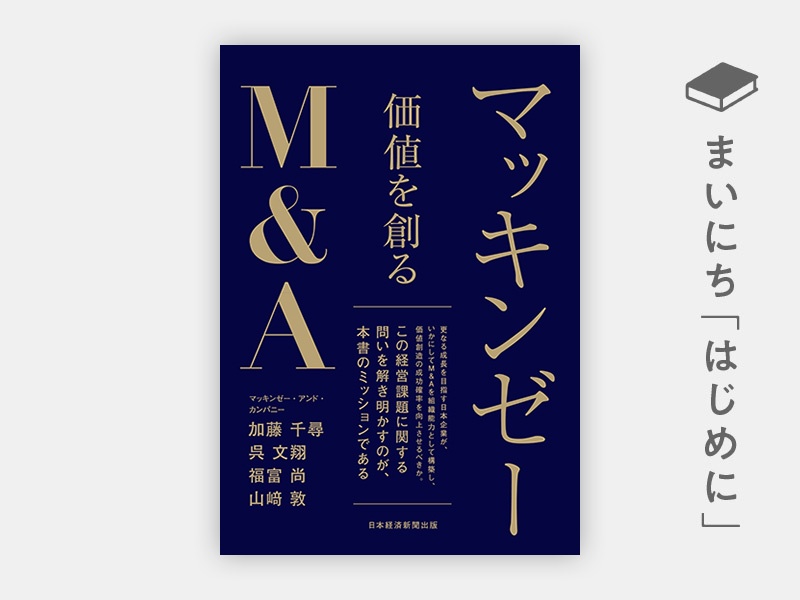 7
7はじめに:『マッキンゼー 価値を創るM&A』
-
 8
8話題の本 書店別・週間ランキング(2024年4月第2週)
-
 9
9もはやひとごとではない物語 石原壮一郎が選ぶ夫婦関係を見直す2冊
-
 10
10「本を贈る日」に日経BOOKプラス編集部員が、贈りたい本 2024
-
 11
11『水曜日は働かない』『昨夜の記憶がありません』など休みを考える3冊
-
 12
12競馬・宝くじと比べれば明快 生命保険は行動経済学的に不合理
-
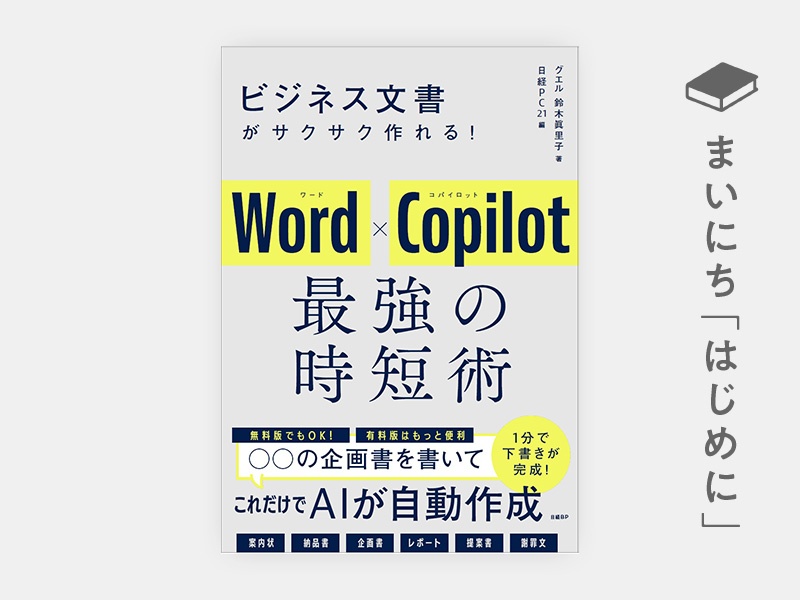 13
13はじめに:『ビジネス文書がサクサク作れる! Word×Copilot 最強の時短術』
-
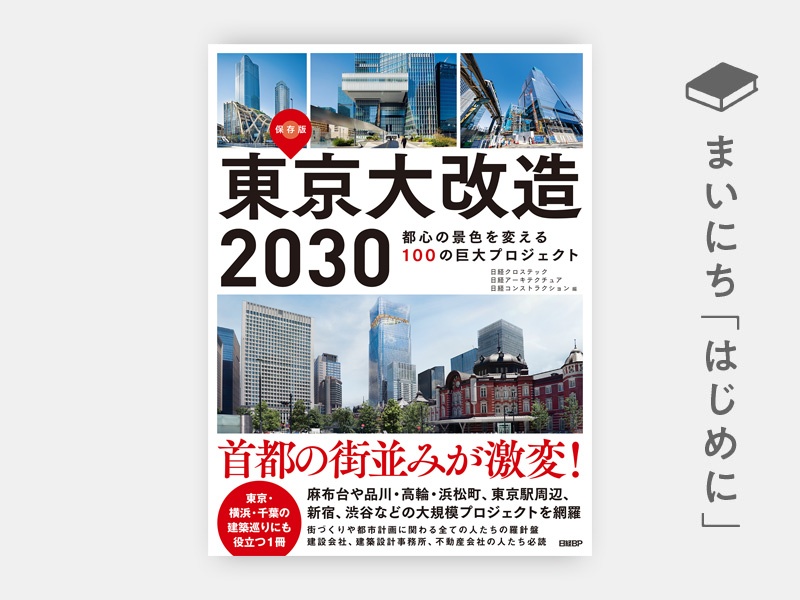 14
14はじめに:『東京大改造2030 都心の景色を変える100の巨大プロジェクト』
-
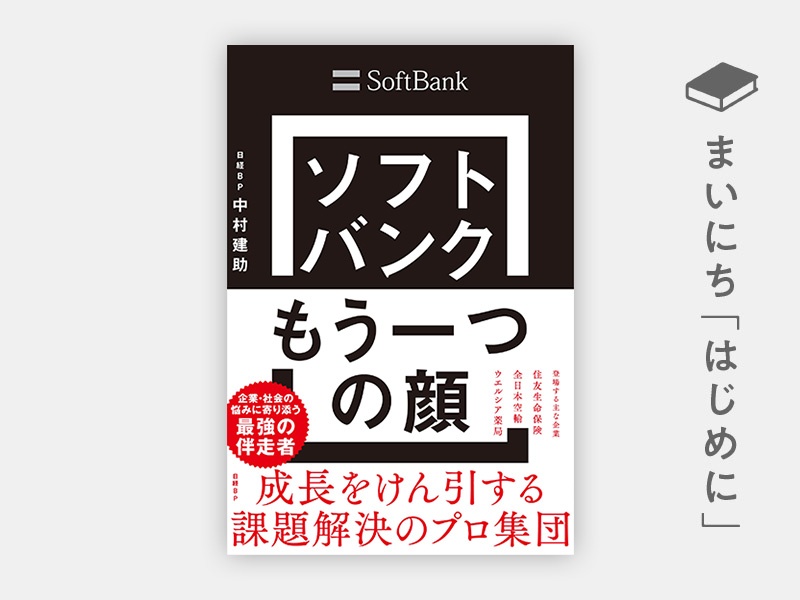 15
15はじめに:『ソフトバンク もう一つの顔 成長をけん引する課題解決のプロ集団』
「本日」は2週間以内に公開した記事が対象
旧サイトをご利用のお客様へ
旧サイトは4月21日より、新サイト「日経BOOKプラス」に統合されました。旧サイトに掲載されておりました書籍ならびに関連情報は「日経BOOKプラス」にてご覧いただけます。
書籍をお探しの場合は、画面上の虫眼鏡アイコンから検索機能をご利用いただき、書名/著者名/ISBN/その他キーワードでお調べください。関連資料やサンプルファイル、正誤表をお探しの方は、各書籍のページ下部からダウンロードしていただけます。
今後とも「日経の本」ならびに「日経BOOKプラス」をよろしくお願いいたします。
企業経営にはSDGsやESGの視点が必須
SDGs・ESG関連書籍はこちら
https://info.nikkei.com/books/sdgs_esg/